
 |
茨城県立高萩清松高等学校 |
Takahagi Seisho Comprehensive Upper Secondary School
創造する自分らしさ |
|
★選べる・学べる 5系列(6分野) |
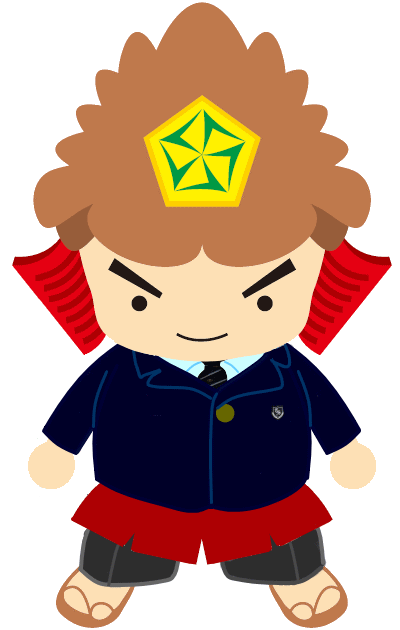 |
〒318-0001 茨城県高萩市赤浜1864番地 TEL:0293-23-4121 FAX:0293-22-2915 Email:ac-koho@takahagiseisho-h.ibk.ed.jp



 |
茨城県立高萩清松高等学校 |
Takahagi Seisho Comprehensive Upper Secondary School
創造する自分らしさ |
|
★選べる・学べる 5系列(6分野) |
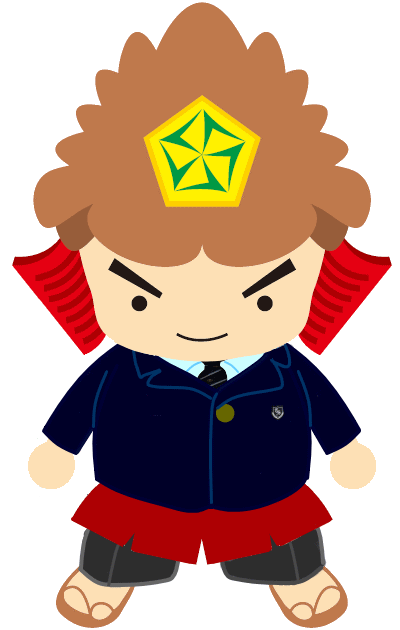 |
〒318-0001 茨城県高萩市赤浜1864番地 TEL:0293-23-4121 FAX:0293-22-2915 Email:ac-koho@takahagiseisho-h.ibk.ed.jp



日曜日、花貫渓谷に行ってきました。花貫渓谷は秋の紅葉が有名ですが、私はこの季節の花貫渓谷も大好きです。新緑の中のモミジ、川沿いに萌える若葉、エメラルド色に輝く渓流、それらが一体となった、自然のたくましさ、美しさ、そして、あふれる生命力を感じてきました。まさに無限の可能性を秘めた、未来への希望に満ちた風景でした。
このすべての命が輝く、春の良き日に、茨城県立高萩清松高等学校に、まさに無限の可能性を秘めた、未来への希望に満ちあふれた新入生、百六名の皆さんを迎えることができ、とても嬉しく思っています。新入生の皆さん、入学おめでとう。そして保護者の皆様方、本日はお子様のご入学誠におめでとうございます。
さて、新入生の皆さん。今私たちが生きているこの現在の時代が、「VUCAの時代」と呼ばれるのを聞いたことがあるでしょうか。
「V U C A」 4つの単語の頭文字をつなげた造語なのですが、一言で言えば、将来の予測が困難な現代を、VUCAの時代と呼んでいます。
また、10年ぐらい前に、イギリスのある研究者が発表した論文の中で、このようなことが言われました。
「今後、10年から20年で、日本の49%の職業が、機械や人工知能、AIによって、取って代わられる可能性が高い」
ここまでの話を聞いてどんなイメージを持つでしょうか。
将来の予測が困難。
今ある職業がAIによって取って代わられるかもしれない。
また、別のこんな調査結果もあります。
最近行われた日本の保険会社の調査です。
中学生に、将来なりたい職業は、と聞いたところ、3位が社長などの会社経営者・起業家、2位がプロのeスポーツプレイヤー、そして、1位がYou Tuber だったそうです。
これらの職業は、私が職業を考えるときには存在しなかった、あまり身近にありませんでした。
そうすると、皆さんが進路を考える頃には、さらに、今、想像もできないような職業が存在しているかもしれません。
あるいは皆さんが自分で新しい職業を作り出しているかもしれません。
そう考えるとワクワクしませんか。
つまり、先ほどの研究者の予測というのは、決してAIが将来、人間の仕事を奪うという悲観的な見方ではなく、将来の人手不足をテクノロジーで解決する可能性、あるいは、将来、人間は創造性やコミュニケーションがより求められる仕事を担うようになる、というような、人とAIとの共存の可能性を示したものとも言えます。
最初に話したVUCAの時代。将来の予測が困難な時代というのは、言い換えれば、自分の未来を自分で切り拓ける時代、ともいえます。
そう考えるとワクワクしませんか。
それでは、自分の未来を自分で切り拓くための、生涯を生き抜く力とは何だと思いますか。
私は「○○力(まるまるりょく・まるまるちから)」だと思います。
この○○に入る言葉を決めるのは皆さん一人一人。
自分が決めた自分なりの「○○力」を、自分の生き方にどう生かしていくかを決めるのも皆さん一人一人。
その「○○力」は、決して3年間で完結するものではないかもしれません。
生涯をかけて、「こんな生き方をしたい」という自分なりの理想の生き方、最近の言葉で言えばwell-being、よりよく生きる、幸せに生きるという意味ですが、幸せに生きるために、自分なりの試行錯誤を続けること、挑戦を続けることを通して、自分だけの「○○力」を探し続けてくれることを願っています。
4月1日、最初の職員集会で、私は先生方と、髙萩清松高校をこんな学校にしていきましょう、ということを共有しました。
その1つが、生徒も私たち教職員も、たくさん挑戦できて、たくさん失敗してもよい場にしましょう、ということです。
「失敗」と聞くと、マイナスのイメージがあるかもしれませんが、挑戦したからこそ、失敗にたどり着ける、その失敗が次の挑戦につながると思うんです。
もう1つが、「ラポール」を大事にしましょう、ということです。ラポールというのは、親和関係という意味で、別の言葉で言えば、「リスペクト」、尊重するといってもいいかもしれません。
「生徒と生徒のラポール」「生徒と先生のラポール」そして、「先生と先生のラポール」
生徒も私たち教職員も、お互いを認め合い、尊重しあえるそんな学校にしましょう、ということを共有しました。
新入生の皆さん、自分だけの「〇〇力」を見つけるために、高萩清松高校での3年間、どうぞたくさん挑戦してください。どうぞたくさん挑戦につながる失敗をしてください。私たちはその挑戦を、その失敗を全力で応援します。
昨日、始業式がありました。在校生にこんな話をしました。
「今、ここにいる新3年生、2年生243人、そして明日入学する新入生106人、あわせて349人の349通りの未来に関われること、寄り添えること、今、とてもワクワクしています。皆さんは、私にとって、先生方にとってかけがえのない宝物です。」
令和6年4月9日、ここ高萩清松高校で新入生の皆さん、保護者の皆様に出会えたことに感謝申し上げ、式辞とさせていただきます。
令和6年4月9日
茨城県立高萩清松高等学校長 塚田 歩


皆さんおはようございます。
この4月から高萩清松高校校長になりました塚田です。
4月1日に初めて高萩清松高校に来ました。先生は高萩清松高校のこと、何より、皆さんのことを早く知りたくて、先週1週間、先生方からたくさん話を聞かせてもらいました。
先生が、「高萩清松高校の生徒たちってどんな感じですか?」って聞いたら、「うちの生徒はみんな純朴で、素直で、かわいい生徒ですよ。」って教えてくれました。まだその時には皆さんと会っていなかったのですが、その話を聞いてとても嬉しかったです。
先ほど、「高萩清松高校校長になりました塚田です」という紹介をしましたが、校長って自分1人でなるものではなくって、先生方がいらっしゃって、そして皆さんがいて初めて校長になれるんですね。今、皆さんとこうして顔を合わせて、私の気持ちを伝えている、まさに今この瞬間、私は高萩清松高校校長になれたのだと思っています。
今後は、みんなのことをもっと知りたいと思っています。授業や部活動の様子をたくさん見に行きたいと思っています。みんなの顔をたくさん見たいです。みんなの声をたくさん聞きたいです。
今日は、先生のこともみんなに知ってもらいたいと思って、先生がこれまで教員として大切にしてきたことを伝えたいと思います。
先生は大学を卒業して20年間、高校で英語を教えていました。教員としての思い出は、何といっても生徒との関わりで、クラスの担任として関わった生徒、英語の授業で関わった生徒、サッカー部で関わった生徒、それぞれの関わりが思い出に残っています。
ふと思うんです。高校で同じ学年に生徒が200人いたとすると、20年間で4000人ぐらいの生徒と関わったことになるんです。
1度きりの人生、という言葉があります。先生も今、1度きりの人生を生きています。
ただ、教員って、これまで関わった4000人の生徒の4000通りの人生に、ちょっとだけですけど関われる気がするんです。
4000通りの人生にちょっとだけですけど寄り添えるような。そんなふうに考えるとワクワクします。
先生が最初に担任をした生徒たちは、今年48歳、最後に担任をした生徒は28歳になります。今、この瞬間も世界のどこかで生きているんですよね。そんなふうに考えるとワクワクします。
たぶんこの先、先生が、卒業生たちに会うことはないかもしれません。
でも、もしかしたら、今日の帰りにたまたま寄ったコンビニで、4000人のだれかに会えるかもしれません。明日どこかで会えるかもしれません。あさってどこかで会えるかもしれません。
そう考えると、当選発表日が毎日続く宝くじを買ったような気がするんです。
そんな宝くじの発表を毎日待ち続けることができる、そんなことを考えるとワクワクします。
去年の9月26日、仕事で会議に出席したら、40歳ぐらいの男性に声をかけられました。
「塚田先生ですよね。僕は32年前、高校1年生で、先生が教育実習のときに教えていただきました。」とのことでした。
まさに、32年前に出会った宝物を見つけることができた瞬間でした。
令和6年度高萩清松高校の校長として、今ここにいる皆さん243人、明日入学してくる新入生106人、全部で349人の349通りの人生に、ちょっとだけですけど関われること、ちょっとだけですけど寄り添えること、今、とてもワクワクしています。
皆さんは私にとって、先生方にとっての宝物です。
期待しています。